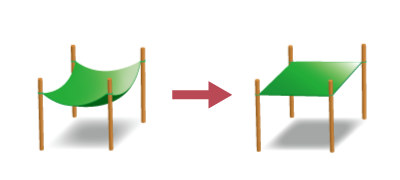語義リストに戻る
慣用表現
根を張る慣用句
ある風習や考え方などが定着する。
寿司を食べる習慣は、ヨーロッパにも完全に根を張ったと言ってよい。
これは伝統短詩型がわが国の社会にいかに根を張っているかを示している事柄なのではないか。(辻井喬(著)『短歌 平成14年3月号(第49巻第4号、通巻637号)』2002)コーパス
勢力を張る慣用句
人や組織が勢力を持つ。
この暴力団は、隣の県にも勢力を張っている。
九州諸方には、豪族が隠然たる勢力を張っている。将来必ず禍乱が発生する。そうなると折角の九州平定が無意味になる。(太田良博(著)『ほんとの歴史を伝えたい』2004)コーパス
宴[祝宴]を張る慣用句
人や組織が宴会を開く。
戦地からの帰還を祝って祝宴を張ることにしました。
鼓や笛の鳴り物があるときには、家来たちも同席が許された。にぎにぎしく宴を張り、このときばかりは飲めや歌えやの大さわぎとなる。(中川なをみ(著)『水底の棺』2002)コーパス
肩肘を張る慣用句
人が、きちんとしなければ、がんばらなければと気負う。あるいは、会が、人にそのように思わせる雰囲気を持っている。
祝賀パーティーとは言っても肩ひじを張った会ではありませんので、気楽においでください。
誰もがこんなパーティなど日常茶飯事という感じで、ドレスアップすることを当たり前とし、肩肘を張った風もなく慣れた雰囲気ですごしている。(辻桐葉(著)『英国紳士の野蛮なくちづけ』2005)コーパス
レッテルを貼る慣用句
人や社会が、一方的にこうだと決めつける。
問題児だとレッテルを貼ってしまうと、その子のよさが見えなくなる。
ただ、一つだけ言えることは、そのあまりにも鮮明な映像が私の心にぴたりと張りついてしまったため、私はそれから逃れることができなくて、思い出すたびに怯えたり怖い夢にうなされたりしたが、それが元で周りの人から小心者のレッテルを張られ、しかられたり、からかわれたり、ずいぶんとひどいいじめを受けたりした。(寄嶋豊(著)『おんびんさくで、どんつくで』2001)コーパス
向こうを張る慣用句
人や組織が、張り合う。対抗する。
競合店の向こうを張って新たな企画を立ち上げた。
漱石研究家のH君の向こうを張って、俺にだってこれくらいのことは出来るんだぞ、と見せつけてやりたい所存である。(半藤一利・荒川博(著)『風の名前風の四季』2001)コーパス
相場を張る慣用句
人が、リスクの高い株の売買をする。
年中相場を張っているようでは、株で儲けることはできない。
よっしゃ!と思える勝ち金額が取れたら金額を落とすか、全く相場を張らないかどちらかにしましょう。なかなかできないですけどね。(Yahoo!知恵袋/ビジネス、経済とお金/株と経済2005)コーパス
山を張る慣用句
幸運をねらって予測をする。
理科のテストで山を張ったが、全てはずれて10点しかとれなかった。
ただひたすら来た球を打つ、というのでは…。これまでの9年間は、何の裏づけもないヤマを張って、はずれていたんやろね。(野村克也・関西スポーツ紙トラ番記者(著)『野村克也全つぶやき すべてのプロ野球ファンに捧ぐ』1999)コーパス
アンテナを張る慣用句
人や組織が、情報をもらさず得られるように注意をする。
優秀なビジネスマンは、常に高くアンテナを張っているものだ。
こんなふうに、私の商売であるレストランにかぎらず、いつでもアンテナを張って見ていますと、商売のヒントがあらゆるところに転がってるもんです。(宇都宮俊晴(著)『仕事を心から楽しめなくて、なにが銭もうけじゃ!実践的「個人商店主義」のすすめ』2003)コーパス
執筆:木下 りか 校閲:籾山 洋介