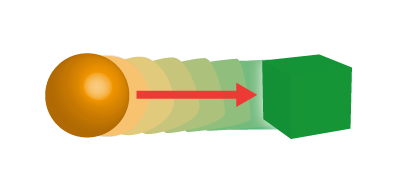語義リストに戻る
慣用表現
毛色がかわる慣用句
性質や種類が異なる。
最近はちょっと毛色が変わった小説が好まれる傾向にあるようだ。
これまでとはだいぶ毛色が変わり、戦争映画というより歴史ものになった。(Yahoo!ブログ, 2008, Yahoo!ブログ)コーパス
人がかわる慣用句
性格がかわって、別人のようになる。「人が{変わった}ように」という形で使われることが多い。
田中さんの息子さんは大学受験に失敗してから、人が変わってしまった。
内気で、人見知りをする性格も、人が変わったように明るくなった。 (日本推理作家協会編 『自選ショート・ミステリー』, 2001, 913)コーパス
かわるがわる慣用句
複数の人やものが交互に同じ動作をする。
宝くじが当たったことを聞きつけた親戚がかわるがわる家にやってきた。
体を横にもできないような窮屈なキャンプ生活のなかで、代わる代わるみんなで歌をうたって、演芸会のようなことをやったりしました。 (五木寛之著 『運命の足音』, 2002, 914)コーパス
相手かわれど主かわらずことわざ
相手が変わっても、本人は常に同じで変化しない
仲田さん、また会社をクビになったんだって。遅刻をくり返して。相手変われど主変わらずとは仲田さんみたいな人のことを言うんだよね。
第三話は、このホテルで娘の結婚式をする両親の話であった。いずれも主演はウォルター・マッソー。相手変われど主変わらぬコメディであった。(小薮田千栄子、川本三郎著、『ポケットいっぱいの映画』、1991)コーパス
所かわれば品かわることわざ
場所が違えば、文化・習慣・言語などが違うものである。
日本ではパンといえば柔らかい食パンが代表的であるが、フランスでは日本のような食パンはなく固いフランスパンが基本である。フランスで食パンがないと気が付いたとき、同じパンと言っても所変われば品変わるものだなと思った。
そして同じ「HONDA」のエンブレムが付いていても、所変われば品変わる、で、いずれのモデルも各々の生産国の2輪市場事情が反映されており、じつにバラエティ豊か。(別冊MOTOR CYCLIST, 2002, 機械)コーパス
秋の夜と男の心は七度かわることわざ
男性の愛情は変わりやすい。
弟は離婚したばかりなのに、もう新しい恋人がいるようだ。「秋の夜と男の心は七度変わる」と言うけれど、まさにその通りだと痛感した。
秋の夜と男の心は7度変わる(要するに、心変わりに男女は関係なくて、人それぞれっていうことですね!)はあまり知られていませんよね!(歌と自然と夢の旅人、2012、はまぞうブログ)コーパス
電話をかわる慣用句
電話を他の人に取り次ぐ
担当の者とお電話を代わりますので、少しお待ちください。
取り次いだサキか電話を代わった琴絵の顔が、一瞬のうちにこわばった。コーパス
目の色がかわる慣用句
何かに対する姿勢や感情が変わることを表す。怒る、驚く、何かに集中するなどの気持ちの変化を表すが、そのような状態になっている様子を表す場合も多い。
テストで100点を取ればゲームが買ってもらえると聞いて、子どもたちの目の色が変わった。
最初は文句ばかり言っていた子どもたちが、やり方がわかったとたん目の色が変わって熱心にやり出し、私語がまったくなくなり真剣になりました。(卯月啓子著、『漢字と遊ぶ、漢字で学ぶ』、2003)コーパス
執筆:永井 涼子 校閲:砂川 有里子