 日本語の問題については,かつて海外子女教育や帰国子女の受入れ体制を整備した頃のこと
を思い出す。当時,国内の教育問題にかまけて,海外の日本人子弟のことは,どこか遠い話
のように思われ,問題への対応が遅れたのではなかったかと反省したものである。
日本語の問題については,かつて海外子女教育や帰国子女の受入れ体制を整備した頃のこと
を思い出す。当時,国内の教育問題にかまけて,海外の日本人子弟のことは,どこか遠い話
のように思われ,問題への対応が遅れたのではなかったかと反省したものである。
 学術審議会に,水谷さんを代表とする「国際社会における日本語についての総合的研究」と
いう創成的基礎研究費(いわゆる新プロ)が提案されたとき,理工系の委員からもこの研究
に対する強い期待が寄せられた。そのご支援と的確な問題意識を伺いながら,日本語教育は
国語学者だけの問題ではない,問題の取り上げ方が遅かったのではないか,といった叱声さ
えも聞こえたように思った。周辺から起こってくる重要な問題について,中心部の反応が
,ここでも後れをとっているのではないかと往時を思いだしたのである。
学術審議会に,水谷さんを代表とする「国際社会における日本語についての総合的研究」と
いう創成的基礎研究費(いわゆる新プロ)が提案されたとき,理工系の委員からもこの研究
に対する強い期待が寄せられた。そのご支援と的確な問題意識を伺いながら,日本語教育は
国語学者だけの問題ではない,問題の取り上げ方が遅かったのではないか,といった叱声さ
えも聞こえたように思った。周辺から起こってくる重要な問題について,中心部の反応が
,ここでも後れをとっているのではないかと往時を思いだしたのである。
 帰国子女の日本語教育が問題にされた頃と比べて,今日,日本語教育の課題は著しく広範な
ものとなり,社会全体に重要な影響を与えるものとなってきた。新ブロが,「国際社会及び
国際化した日本」の中で日本語がどのような役割を果たし,そこにどの様な問題があり,国
際的に日本語を普及させる政策的観点をも視野に入れて,「総合的研究」を進めようとする
ことは,我が国の将来を切り開く大きな意味がある。
帰国子女の日本語教育が問題にされた頃と比べて,今日,日本語教育の課題は著しく広範な
ものとなり,社会全体に重要な影響を与えるものとなってきた。新ブロが,「国際社会及び
国際化した日本」の中で日本語がどのような役割を果たし,そこにどの様な問題があり,国
際的に日本語を普及させる政策的観点をも視野に入れて,「総合的研究」を進めようとする
ことは,我が国の将来を切り開く大きな意味がある。
|
 学習者の範囲をみても,日本への留学生はもとより,日本語を勉強に来る就学生,技術技能
を学ぴに来る研修生,来日するピジネス関係者や学術研究者,さらには,インドシナ難民,
中国からの帰国者,就労を目的に来日する中南米等からの日系人及びその子弟,国際結婚を
した外国人配偶者,さらには日本語を学ぽうとする外国人児童,生徒,学生など,誠に多彩
となり,その総数は国内で八万人,毎外で百六十万人を数えるという(日本語教育の概観,
日本語教育学会
学習者の範囲をみても,日本への留学生はもとより,日本語を勉強に来る就学生,技術技能
を学ぴに来る研修生,来日するピジネス関係者や学術研究者,さらには,インドシナ難民,
中国からの帰国者,就労を目的に来日する中南米等からの日系人及びその子弟,国際結婚を
した外国人配偶者,さらには日本語を学ぽうとする外国人児童,生徒,学生など,誠に多彩
となり,その総数は国内で八万人,毎外で百六十万人を数えるという(日本語教育の概観,
日本語教育学会 1995年2月)。 1995年2月)。
 当然ながら,内外にわたる教師の養成訓練,それぞれに即した教授法の開発,教育内容,教
材や辞書の整備,日本語能力の評価など,多面にわたって必要な施策を総合的に進めて行か
なけれぱならない。その折り最も必要なことは,学習者の類別に対応した日本語教育の支え
,即ち学問的な研究資料を提示していくことである。
当然ながら,内外にわたる教師の養成訓練,それぞれに即した教授法の開発,教育内容,教
材や辞書の整備,日本語能力の評価など,多面にわたって必要な施策を総合的に進めて行か
なけれぱならない。その折り最も必要なことは,学習者の類別に対応した日本語教育の支え
,即ち学問的な研究資料を提示していくことである。
 これらの体制を整えるためには,大きな政策努力を必要とする。然し,日本語の理解者を増
やし,日本語で意志疎通を図ることができる場合の政治的,経済的,文化的な行動力の大き
さは計り知れないものがある。自動翻訳の手法が開発され,活用されたときの効果も絶大で
あろう。もし,日本語が国際的用語として使用されるようになれば,我が国の発信能力は幾
層倍にも大きくなるはずである。
これらの体制を整えるためには,大きな政策努力を必要とする。然し,日本語の理解者を増
やし,日本語で意志疎通を図ることができる場合の政治的,経済的,文化的な行動力の大き
さは計り知れないものがある。自動翻訳の手法が開発され,活用されたときの効果も絶大で
あろう。もし,日本語が国際的用語として使用されるようになれば,我が国の発信能力は幾
層倍にも大きくなるはずである。
 日本語についての総合的研究であるこの新プロ「日本語」が,このような政策課題に対して
も,寄与しうるものとなることを心から期待するのである。
日本語についての総合的研究であるこの新プロ「日本語」が,このような政策課題に対して
も,寄与しうるものとなることを心から期待するのである。
|
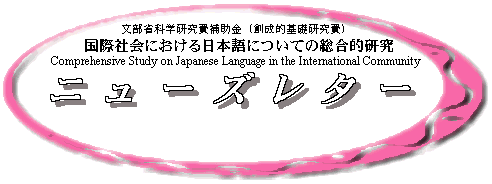
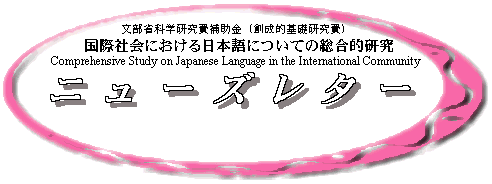

(財)新・国立劇場運営財団・理事長
新プロ「日本語」評価委員
木
田

宏