シンポジウム:複文構文の意味の研究 概要
- プロジェクト名
- 複文構文の意味の研究 (略称 : 複文構文)
- リーダー名
- 益岡 隆志 (神戸市外国語大学 教授,国立国語研究所 理論構造研究系 客員教授)
- 開催期日
- 平成24年12月15日 (土) 13:00~17:40
平成24年12月16日 (日) 10:30~16:00 - 開催場所
- 国立国語研究所 2階 講堂
発表・質疑 概要
発表資料をPDF形式でご覧いただけます。
平成24年12月15日 (土)

以下の4つの講演が行なわれた。これら4つの講演は,本プロジェクトの4つの班 (連用複文構文・連体複文構文,文法史,コーパス言語学,言語類型論・対照言語学) にそれぞれ対応するものである。
「名詞節か副詞節か ―「の節」の名詞性・節性の検討―」天野 みどり (和光大学)
発表資料 [ PDF | 379KB ]

ベースである構文からの変容という見方のもと,従来の研究において副詞節あるいは副詞節的とみなされてきた「のが節」・「のを節」が名詞化された「の節」に格助詞が付与されたものと見るべきであることを論じた。
「接続部における名詞句節の脱範疇化について」青木 博史 (九州大学 / 国立国語研究所客員)
発表資料 [ PDF | 353KB ]

格助詞から接続助詞へという通時的変化の可能性をめぐって,「が」・「を」・「に」の場合を対象に検討を行った。また,古代語から近代語への変化として,述語重視から機能語重視へという変化が注目されることを論じた。
「日本語コーパスと複文の研究」田野村 忠温 (大阪大学)
発表資料 [ PDF | 537KB ]

「現代日本語書き言葉均衡コーパス (BCCWJ) 」の特性を解説したうえで,複文研究に対するBCCWJの活用の有効性を示すとともに,現状における困難性―具体的には,離れた形式間の呼応関係や構文の意味的な側面の研究の困難性―を指摘した。
「従属句の類型を再考する」大堀 壽夫 (東京大学)
発表資料 [ PDF | 201KB ]

Role and Reference Grammarの枠組みによる文の階層構造と接続構造の見方を説明したうえで,階層の動機づけについて論じた。さらに,それに基づき,南不二男による従属句の類型 (「A類・B類・C類」) の見方を検討し,その現代的意義と再考されるべき点を論じた。
平成24年12月16日 (日)
本プロジェクトの中間報告を4つの班別に行った。これらの中間報告では,研究動向 (研究史を含む) ,本プロジェクトにおける取り組み,今後の課題などが示された。


連用複文構文に関する報告前田 直子 (学習院大学)
発表資料 [ PDF | 301KB ]
連体複文構文に関する報告大島 資生 (首都大学東京)
発表資料 [ PDF | 210KB ]
連用複文構文・連体複文構文にかかわる代表的な研究を整理したうえで,本プロジェクトで行われた研究発表をそこに位置づけるとともにその意義を述べた。さらに,今後取り組むべき具体的な研究課題を提示した。
文法史に関する報告橋本 修 (筑波大学)
発表資料 [ PDF | 248KB ]

複文構文にかかわる文法史研究の流れ ( (i) 1980年代まで, (ⅱ) 1980年代・90年代, (ⅲ) 2000年代以後) を辿り,併せて,最近の研究動向を整理して示した。そのうえで,現在の課題の具体的事例を掲げるとともに,今後の課題・期待について述べた。
コーパス言語学に関する報告丸山 岳彦 (国立国語研究所)
発表資料 [ PDF | 224KB ]
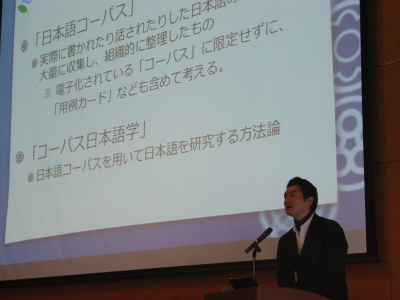
日本語コーパスの開発史について国立国語研究所での取り組み―南不二男の複文研究が初期のコーパス言語学の成果として位置づけられることなど―を中心に解説した。さらに,係り受け関係などのアノテーション情報の整備などを今後の課題として挙げた。
言語類型論・対照言語学に関する報告堀 江薫 (名古屋大学)
発表資料 [ PDF | 393KB ]

言語類型論・対照言語学に貢献し得る事例として,寺村秀夫の連体修飾節の研究や南不二男の従属句の階層性の研究を挙げた。さらに,主節的な現象が従属節のなかで実現する「主節現象」や従属節が主節化する現象が,語用論とのかかわりなどにおいて注目されると論じた。
全体討議

これらの報告に続いて,全体討議を行った。全体討議では,中間報告で示された内容・論点などに対する質問・コメントがフロアから寄せられ,報告者とのあいだで活発な意見交換がなされた。
